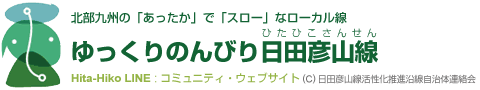歴史
日田彦山線の発祥は、他の筑豊地域の例にもれずに鉄道による石炭輸送に起源を発します。その変遷を以下のようにまとめてみました。
明治29年(1896)2月5日
伊田(現田川伊田駅)~後藤寺(現田川後藤寺駅)間が当時の豊州鉄道の手によって開業。開業の目途は、すでに同鉄道により開業されていた田川線(現平成筑豊鉄道)行橋~伊田間の延伸でした。

明治32年(1899)7月後
藤寺~川崎(現豊前川崎駅)間が開業。
明治34年(1901)
九州鉄道が豊州鉄道を合併。
明治36年(1903)12月
川崎~添田(現西添田駅)間が開業。
明治40年(1907)7月1日
九州鉄道、国有化。
大正4年(1915)4月1日
小倉鉄道が東小倉~上添田(現添田駅)を開業。

昭和12年(1937)8月22日
夜明~宝珠間が開業。
昭和17年(1942)8月25日
国鉄により田川線の添田駅(現西添田駅)と小倉鉄道の上添田(現添田駅)が結ばれ、彦山駅まで開業。

昭和18年(1943)5月
国鉄により小倉鉄道が買収され、同社が保有したいた東小倉~添田間の線は国鉄添田線となる。これにより、添田駅は添田線の終点であると同時に、田川線の線路も通る駅となりました。
昭和21年(1946)9月20日
宝珠山~大行司間が開業。
昭和31年(1956)3月15日
彦山~大行司間が開業し、城野~石田間も短絡線で結ばれたため、ここにきて別々に存在していた北からの路線と南からの路線が1つとなり、日田線と命名されました。また、東小倉~石田間は貨物沿線となりました。その結果、東小倉を出た列車は添田、彦山などを経由して夜明まで行き、そこから久大本線に入って、観光地の日田まで走るようになりました。
昭和32年(1957)10月1日
香春~田川間線の短絡線が完成。
昭和35年(1960)4月1日
城野~後藤寺~夜明間は日田彦山線になり、香春~添田間が添田線となりました。(昭和60年(1985)添田線は廃線)
- 参考資料
-
- 福岡鉄道風土記(1999年1月16日初版発行) 著者/弓削信夫 発行者/三原浩良 発行所/葦書房有限会社 福岡市中央区赤坂3丁目1番12号
- JR全線全駅(1995年11月15日発行) 発行人/池田浩規 編集者/遠藤法利 発行所/弘済出版社 東京都豊島区北大塚1丁目16番6号
- 写真および写真解説提供: ©写真紀行★風にふかれて